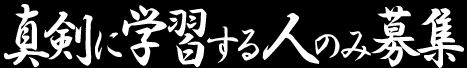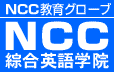|
1日から5番目の社会保険制度である介護保険制度が実施された。
さまざまな問題を抱えたままのスタートとなったとはいえ、介護保険の導入によって少なからぬ人が恩恵を受けるのも事実である。
〔英会話表現による言い換え〕
問題点はできるだけ早急に改善しながら、大事に育てていかなければならない。
1997年12月の介護保険法の成立以降、国も市町村も今年4月からの実施に向けて準備を進めてきたが、現時点で「ほぼ万全の準備が整った」と自信を持って言える市町村は少ないようだ。
国が作成した要介護の認定基準(認定ソフト)が実情に合っていないため、多くの自治体が公平公正な認定ができないと不安を抱いている。
<英語にて解説:要介護の認定基準>
また、認定を終えても、具体的なサービスの内容などを定めた介護サービス計画(ケアプラン)作りが十分にできないまま今月のスタートを迎えた市町村も目立つ。
ケアプランを作成する介護支援専門員(ケアマネジャー)の数が少ないことも懸念されている。
《「ケアマネジャー不足の原因」について英会話/ディスカッション》
介護保険では、制度を運営する主体である市町村の裁量権が大きい。
市町村が住民と話し合いながら独自の行政を行うことが可能だ。
介護保険のメニューにないサービスの提供や介護の質を上げるための工夫など、すでに各自治体が個性を出し始めている。
介護保険を地方分権の試金石とみる向きも多い。
[「介護保険と地方分権」を英会話/ディベートのテーマとして]
1989年、「自助と家族の相互扶助」を重視した「日本型福祉」と呼ばれた政策の転換を模索する動きが出てきた。
「日本型福祉」は、第1次石油ショックによる影響で経済が戦後初めてマイナス成長を経験した時代に登場した。
《「「日本型福祉」登場の背景」に関して英語論説》
福祉予算の抑制・削減という意図がその根底にあった。
89年に発足した介護対策検討会の報告書は「介護サービスは、住民に身近な市町村を中心に施策を展開すべきである」とうたっている。
介護が必要なお年寄りの世話を、家族だけに任せず、社会全体で担おうというものだ。
〔英会話用の口語文体で言い換え〕
「日本型福祉」は、介護期間が長期化し、介護をする側の高齢化が進む中、介護家族に「介護地獄」をもたらし、「自助と家族の相互扶助」ではお年寄りもその家族も救われないことが明白になった。
《「介護地獄の実態」について英語記事》
こうした経緯から、介護保険が導入されることになったのである。
従来は措置制度のもと、行政が介護サービスの内容などを決めていたが、介護保険では個々の利用者がサービス事業者と契約を結び、サービスを利用することになっている。
介護サービスに競争を導入した形だが、トラブルや苦情に備える仕組みが現状では不十分だ。
<英会話/ディベート:介護サービスへの競争の導入>
介護保険法ではサービス会社などに契約書の作成が義務づけられていない。
サービスが契約通りに提供されているかなどをチェックする第3者機関がない。
苦情やトラブルの相談窓口もはっきりしない。
苦情やトラブルへの適切な対応は、制度を利用者にとってよりよいものにしていく上で欠かせない。
[「介護保険制度の問題点」を英会話/ディスカッションのトピックとして]
|